特許事務所に入所して5か月が経過しました。学んだことを列挙していく。
異業種転職で未経験でも明細書の理解はできるの?
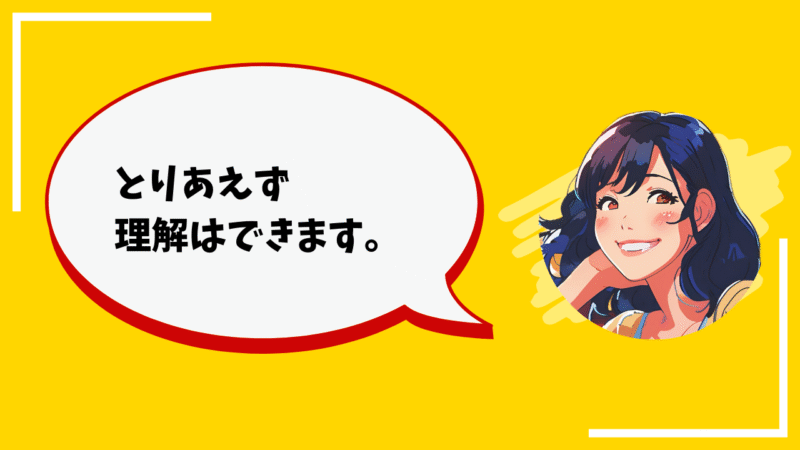
どうも、ニシジマ(@nishijima1029)です。今回は、完全未経験異業種転職(前職は大学受験予備校の職員でした)で、特許事務所に入所して5か月が経過した私が、日々の明細書、意見書作成を通じて学んだことや気づきをお伝えする記事でございます。
ということで、学部卒でも発明の理解ができますか?というところからなんですが、まあ一応、全く何もかもわからない!みたいなことになりません。ちなみに化学科卒で、全く化学とは別の分野の特許技術者をしておりますが、明細書に何が書いてあるのか全くわからない!ということはありません。
5か月働いてみてたどり着いた結論は、弁理士のお仕事は具体的な事象から公式を見つけ出すお仕事なのかもしれないということでした。
入所初日はそもそも明細書を読んだのが人生初だったので、かなり面喰いました。誰でも見れる公開公報などをJ-Platpatなどで検索していただければ、明細書がどういうものなのかわかるかと思いますが、かなり独特な文章構成となっています。そのため、初めて読んだ方はきっと、「日本語で書かれてるのに何が言いたいのかわからん!」と嘆くこと必至です(正直、入所2~3か月くらいはマジで何もわからなさ過ぎてやっていけるかな…?と内心ビビってました)。
わからなさ過ぎてというのは明細書の内容がわからないというのもあるのですが、どういう着眼点で、どういうところに視点を置いて文章を読んだり書いたりするべきかなどが全く分からなかったです。意図がわからないといった感じでしょうか。すごく文章が独特なんですよ。「~でもよい」っていっぱい出てきて、結局何が言いたいの?みたいなのとか。
しかし、読み進めて何度も何度も読んでるうちにとりあえずの理解(100%ではない)はできるようになります。ただ、どうしてそのように文章が構成されているのかであったり、ここのその文章を挟み込んだ意図であったり、そういったことまでは正直5か月経過した今もやはりあやふやです。書いてある内容の意味はとりあえずわかると言ったところですね。多分、理系の学部卒の方であればとりあえずは読めるんじゃないですかね。分野にも依りますし、初日からいきなりスイスイ読めるということはないでしょうが。
文章の意図がわかるようにならないと明細書を作成したり、意見書を書いたりするのができないので、この辺りは今後研鑽しようと思っております。弁理士試験で学んだことを実務でやってる感じで、まさに日々日々、知行合一って感じです。
日常であふれている算数の問題があるじゃないですか。あれを概念化するようなイメージです。3つあったプリンを食べると2つになっていたり、高いダイヤのネックレスを買うと財布の中身が空っぽになっていたりする日常があるじゃないですか。あれを概念として捉えるのは難しくないですか。具体であふれた日常を公式にする作業をしています。
まあそんなこんなで、今日は初日は何もわからなかったけど、こういうことまで考えられるようになったよ!気づいたよ!という成長報告回です。5か月働いたらこんな感じになりますというサンプルです。
弁理士試験と実務を通して気づいたこと
特許明細書は抽象的で難しい?
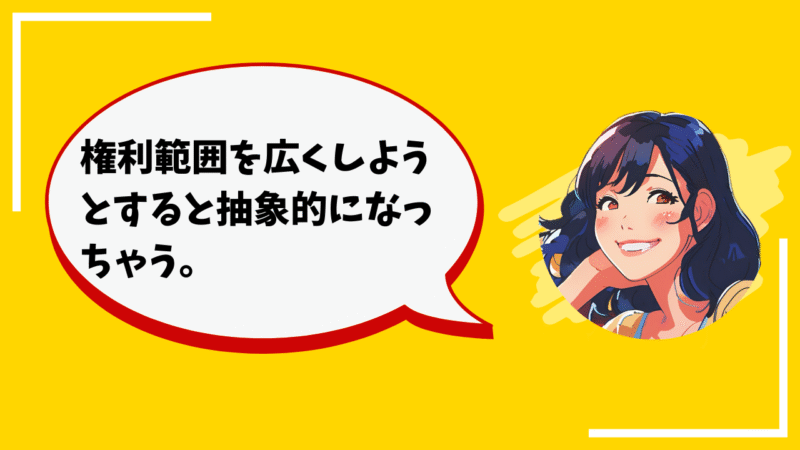
例えば、意匠権って、類似範囲まで権利範囲に含まれるじゃないですか。でも、特許権というのは原則、特許請求の範囲が権利範囲であって、いわゆる同一の範囲(引き延ばしても均等論まで)までしか権利範囲とは言えないですよね。
これは要するに、意匠登録出願で作る書類(願書の記載と図面)というのはすごく具体的なんですよね。具体的だからこそ、ちょっとずれたら非侵害であるとすると、ちゃんと保護が図れないわけです。だから類似範囲まで権利範囲を拡げているわけですね。一方で、特許出願というのは権利範囲は特許請求の範囲(文章)なんです(逸れますが、意匠の難しさもあると思います!)。解釈に余地があるんですよね。
つまり、出願段階で、いかに特許請求の範囲を拡げる文言で書くかが弁理士の腕の見せ所なんですよね。つまり、特許出願で作る明細書や特許請求の範囲というのはかなり抽象的な文章になってるんですよ。色んなものを包含するために。
発明者は具体的な発明を持ってきますよね。それをそのまま文章にすれば良いわけじゃないんです。弁理士が発明者の話を聴いて、具体化された発明を概念的に理解し、文章に起こす必要があるわけです。これがめちゃくちゃ難しい。特許出願や意見書や補正書を考えるのは、頭の中で具体をいかに抽象にもっていけるか(又はそれの逆)みたいなところが勝負どころみたいなところがあるわけです。
具体化された実物を概念として捉える力みたいなものが要るような気がします。これがめちゃくちゃ難しい。できる限り包含するけど、公知技術は踏まない文章を作成するのです。むちゃくちゃ難しい。
公開公報などで明細書を見ていただくとわかるかと思いますが、あまりに抽象的な文章で最初は面食らうと思います。何が言いたいねんと。
無価値な特許も価値がある?
無価値な特許というのは、無効理由を存する特許権や、実質的に機能しないような権利範囲が狭すぎる特許権を指します。こういった特許権って、素人目にはあんまり意味がなさそうじゃないですか。だって、無効審判請求したら遡及消滅して終わりですからね。無効審判請求するまでもなく、侵害訴訟提起されたとしても、無効の抗弁をされたら終わりですからね。
それでも価値があるんです。例えば、車の部品一つを取ってもすごい数の特許権があるそうです。ということは、この一つの部品(例えば何とかギヤ)に10個も20個も特許権があったとすると、競業他社としては実施するのが怖いんですよね。無効理由があるかどうかもちゃんと調べないといけませんし、実際訴訟になったときにちゃんと無効の抗弁が認められるかどうかもわかりません。
そうすると、無効理由はあるかもしれないけど調べるのが大変だし、できる限り特許権に触れないような実施をしていこうとなるわけです。実際は無価値な特許権だとしてもお守りになるというわけです。
つまり、無効理由はあっても良いから(無いに越したことはないが)特許査定をもらうということには一定の価値があるということらしいです。弁理士試験だけ勉強をしているときは思いつかない発想ですよね。
新規性欠如のクレームを限定補正するときは単一性違反に注意?
新規性欠如(29条1項違反)、進歩性欠如(29条2項違反)で拒絶理由通知を打たれたCL1があったとします。これに対して手続補正書と意見書を作成するとします。そして、CL1に構成要素Aを足した補正後のCL1を作成します。と同時に、CL1に構成要素Bを足した補正後のCL2を作成し、CL1に構成要素Cを足した補正後のCL3を作成した手続補正書を作成するとします。
補正前
- 補正前のCL1(29条1項、2項違反)
補正後
- CL1(補正前のCL1+構成要素A)
- CL2(補正前のCL1+構成要素B)
- CL3(補正前のCL1+構成要素C)
こういった補正をした場合、実はこれ単一性違反(37条違反)の拒絶理由になってしまうんですよね。厳密には。だって、CL1は新規性がありませんし、「単一性」というのは、同一の又は対応する特別な技術的特徴を意味しますから(審査基準参照)。
「特別な」というのは簡単に言うと、新規性あり以上進歩性あり未満くらいの意味だと思えば多分合ってます。ということで、補正後のCL1とCL2とCL3の同一の技術的特徴(構成要素)はまさに補正前のCL1なんですよ。補正前のCL1、即ち同一の技術的特徴が新規性がないのですから、こういう補正は単一性違反になるのです。
言われればわかりますが、実務でこういう補正をしようとしていても気づかないですよね。なるほどな~と思った次第でした(感心している場合ではない)。
補正したのに同じ理由で拒絶ってどういうこと?
最初の拒絶理由通知が打たれた後、補正をしたら必ず最後の拒絶理由通知は来るでしょうか?答えは×です。実は、最初の拒絶理由通知が打たれた後に補正をして、同じ拒絶理由だった場合、最後の拒絶理由通知は打たれることなく、拒絶査定されることになります。
これは(多分ですが)、特許法50条本文が根拠条文となっています。
「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない」
同じ理由って意味わからなくないですか?どういう意味で同じ理由?だって、補正をしたんですよね。百歩譲って意見書のみで反論した場合は権利範囲の客体(CL)は変わっていませんから、同じ理由で拒絶される可能性はあるでしょう。でも、手続補正書を提出して補正をした場合は、構成要素が追加されたり、減縮したり何らかの形でCLの内容が変わっているわけですから、全く同じ理由にはならないと思うんですよね。
しょぼーい構成要素を追加して反論したとしても、そのしょぼーい構成要素のせいで厳密には全く同じ理由にはならないんですよ。だから弁理士試験の勉強をしながら、大学受験予備校で働いていたときはピンと来ませんでした。
しかし、ここでいう「同一」という言葉の意味は同一証拠(引例)に基づき、同一の条文での拒絶理由(例えば進歩性欠如)という意味合いらしいです。つまり、私が当初思っていたよりも広い意味で「同一」ということです。であれば、意味が解りますよね。
こんな風に、「同一」ってどういう意味合いで同一なの?と考えるようになりました。
39条2項違反の「同一」の発明について同日に二以上の特許出願があったときの「同一」も気になりますよね。多分、審査基準を読めば書いてあるんだと思います。さすがにこれは文言同一の意味合いではないと思われます。文言同一やったらそんなん神業(カンニング)やんw
明細書を補正する意味ってある?
明細書って補正する意味あるんですか?って話です。多分、意味ないですよね?だって、CLに構成要素を追加することで限定する補正をしたとします。そのときに明細書を補正する意味って何もなくないですか。
明細書にはサポート要件(36条6項1号)が課されています。なので、出願段階でちゃんとCLの内容は書かれているはずなんですよ。後から書き加えたと認定されたら、新規事項追加(17条の2第3項違反)の補正を疑われかねないですし。
だから、明細書って補正する価値って全くないと思うんです。あるんですか?補正をして新規事項追加を指摘されたらヤブヘビですよねぇ。
クレームを読むときに実施例に引っ張られがちになります・・・
クレームって、めちゃくちゃ抽象的ですごく概念的な文章なんですよね。あまり具体的な名称で説明しないんですよ。「突起部」とか「篏合部」とか「延在する」とか。だから、何を指しているのかが本当にわかりにくい。わかりにくいから、実施例に照らし合わせて、何が書いてあるのかを理解しようとするのですが、クレームの文言を実施例で指している意味合いと同じ範囲に解釈してしまうんですね。これは良くない。
例えば、「連結部」という文言があったとして、「連結部」とは実施例で言ってるところの「連結部」ではなくて、概念としての「連結部」なんですよね。「嵌合部」とかもそうだと思います。実施例のように「嵌合」しているところを指して「嵌合部」とは言ってないのです。あくまで概念的に嵌め合わさっているところを指しているのであって、実施例は単なる一例なんですね。
概念的にCLを書くことで包括的な権利を取得できますから、具体的に書くのはあまり良くないんですよ。下位CLで限定する従属項として書く分にはありですが、基本的には不明確(36条6項2号)と言われない限りはできる限り上位概念で公知発明を踏まない文章が理想なのだと思います。
とにかく、概念として具体を捉えるというのはめちゃくちゃ難しいです。日常であふれている算数の問題があるじゃないですか。あれを概念化するようなイメージです。3つあったプリンを食べると2つになっていたり、高いダイヤのネックレスを買うと財布の中身が空っぽになっていたりする日常があるじゃないですか。あれを概念として捉えるのは難しくないですか。具体であふれた日常を公式にする作業です。
弁理士って、具体的な事象から公式を見つけ出すようなそんなお仕事なのかなと思ったりします。
全ての実施例を包含するクレームが良いクレーム
全ての実施例を包含して、尚且つ進歩性を出せるクレームというのが良いクレームなわけです。実施例に留まらず、あらゆる形態を含めたクレームが良いクレームなわけです。権利範囲がそれだけ広いということですからね。でも、一方で、含めれば含めるほどどんどん抽象化して曖昧な文章(36条6項2号違反)になってきちゃうし、含めれば含めるほど新規性、進歩性がなくなってきて公知技術と同一に近くなってくるわけです。
この塩梅を上手に料理して文章を作るというのが弁理士の腕の見せ所らしいですが、本当に今まで書いてきたあらゆる文章(予備校での模試作成、ブログ記事など)に比べて断然に何倍も難しいです。どうして難しいかというと、視点があまりに多すぎるのです。
予備校の模試作成であれば、「生徒に分かりやすく一義的に理解できるものを」というのをモットーにそっちの方向に走り続けて文章を書けば済みます。しかし、特許明細書というのは本当にあらゆることを考えて色んな視点から文章を書く必要があるんです。「分かりやすく」書けばオッケーなんていう単純なものではないのです。何なら実施可能要件(36条4項1号)を超えられるのであれば、寧ろわかりにくく書くべきだったりしますからね。公開の代償として独占権を付与するわけですから。
そうでなくても、分かりやすい文章という視点だけではなく、どうすれば権利範囲が拡がり、またどうすれば拒絶理由通知が打たれたときに対応できるような補正案を仕込んでおくか、そして権利化された後に参酌される明細書をどのように書いておけば侵害訴訟の場で有利に働くかなど全てを考慮した塩梅の取れた文章を書くというのは並大抵のものではありません。
しかも、技術理解は当然のことで、法律上の要件を満たした文章という視点も必要になってきます。外国出願などであれば、拒絶理由通知が中国語や英語で来たりもします。技術理解、法律知識、語学力、そして国語力を兼ね備えた文章を作成するというのはニシジマレベルであってもかなり難しいのです。
弁理士のお仕事は、知識の総合格闘技みたいなところがありますね。
進歩性と均等論は似ている?
OA対応をする際に、進歩性欠如に対する反論をすることがあります。その際によく読むのが進歩性の審査基準。何をもって進歩性があるのか、また無いのかということを理解していないと反論の仕様がないんですよね。それで、長々と書かれた審査基準を読んでいるとふと感じたことがありました。
審査段階でいう「進歩性」というのは、侵害訴訟の場面での「均等侵害」の考え方と何だか似ているというかそんな感じがしたんですよね。
そりゃあそうなんですが笑 対象製品が進歩性を有するのならば均等ではないわけですし、逆に対象製品が大したことがない製品で、「異なる部分」が本質的でないんだとしたら、いわば公知技術(侵害訴訟の場面だと、特許権の技術的範囲)から見て、進歩性がないということですからね。
こうやって、日々弁理士試験で得た知識を実務経験を通して「なるほど~」と学んでおります。
許可クレーム限定で、下位クレームの許可クレーム限定は作る意味がある?
例えば、こんな感じのCLで特許出願をし、拒絶理由通知が来たとします。
- CL1(進歩性欠如)
- CL2(CL1に従属する請求項で、進歩性欠如)
- CL3(CL1又はCL2に従属する請求項で、許可クレーム)
この場合、許可クレーム限定という補正方法があります。CL3をCL1との引用関係を解消し、独立請求項とする補正です。この補正をするときに、数学っぽく考えると、CL1をCL3で限定する補正をすれば十分なような気がします。CL2はCL1の下位概念ですので、CL1をCL3で限定する請求項(CL3を独立請求項にしたもの)さえあれば、CL2をCL3で限定する請求項は包含しているはずなのです。
なので、わざわざCLが増えてしまい、料金がかさんでしまう増項補正となってしまうよりも、CL1をCL3で限定すれば十分というのが原則だと思います。しかも、CL3は許可クレームなのですから、単純に書き下しただけのCL1をCL3で限定する請求項は既に審査官のお墨付きで、ほぼほぼ特許になることは確定しているわけです。
しかしそれでもなお、CL1よりも下位のCL2を、CL3で限定する請求項を作ることも無意味ではないということらしいです。
ちょっとうまく説明できませんが、侵害訴訟などの場面で、より具体的な態様がCL(技術的範囲)になっていれば特許権者としては有利に働きやすいということだそうです。つまり、上位概念で包含しているから、対象製品は技術的範囲に属しているのだという主張よりも、より具体的になっている下位クレームで技術的範囲に属しているのだと主張する方が侵害を認定しやすくなったりするそうです。
また、上位のCL1をCL3で限定するクレームが無効審判で遡及的に消滅する蓋然性も高い場合があります。つまり、審査官の認定が誤りのまま特許査定になってしまい、侵害訴訟の場で侵害者側が無効の抗弁をし、侵害を問えなくなる蓋然性もあるということらしいです。
なかなか実務は深いですよね。そう単純に、上位概念が取れてるんだから下位概念を取る必要はないといった杓子定規な脳死思考ではダメみたいですね。
実務経験と弁理士試験を並行して・・・
ということで、事務所では実務経験を通して勉強をし、家に帰ってからは口述対策の毎日です。まあそんなに気合い入れて口述対策しているわけではないのですが…笑
まあ、のんびりマイペースに頑張っていこうと思います。生き急いでも仕方ないですし、年ッと構えてやっていこうかなと。やること多いんよ…。ほんまに前途多難。
まあでも何とかなりそうですよ。多分。弁理士試験も実務も。何だかんだで、何とかなるんだと思います。入所前は(賢い人いっぱいだし、やばいよな~。ついていけなかったらどうしよ~。)とか思ってましたが、どうにかこうにかなるもんです。特許事務所に転職しようかな?とか思ってる人はぜひやって見てください!
あと、無駄な会議とか意味わからん印鑑をもらいまくるために上司追いかけまくるとかなくなったのはマジで良い。これ意味なくね?と思うことが少なくなった!のは快適かも?

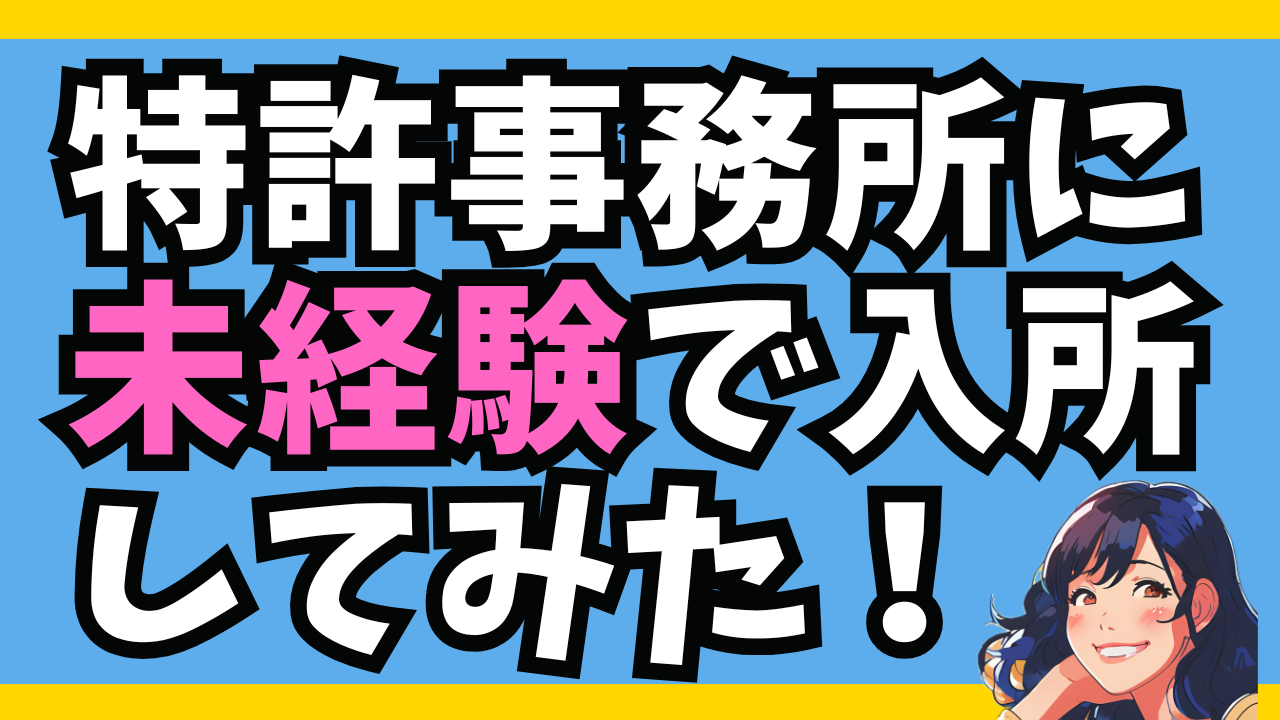
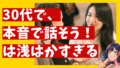
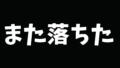
コメント