試験が近づいてくると気持ちがしんどくなる
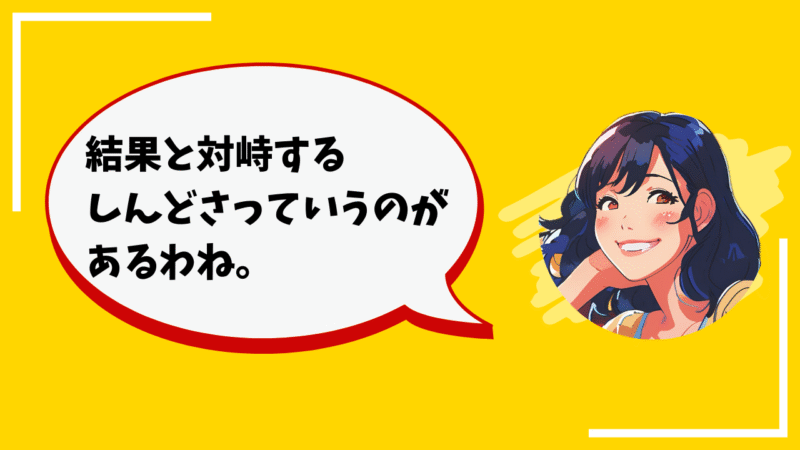
どうも、弁理士試験受験生のニシジマ(@nishijima1029)です。試験が近づいてくると気持ちがしんどくなります。選択科目民法を控えた私です。
合格するための素養って何でしょうか?結論は忍耐力です。泣き言を言うスタンスってめちゃくちゃずるいっていうしょっぱい話を今日はします。
ところで、試験直前期になるとどうしてしんどくなるんでしょうか。結果と対峙しなければならないタイミングがきたからです。
今までは日々勉強をしていれば、充足感を得られていた。「頑張っている」ということだけで何となく満足できていた。だけど、いよいよ結果と対峙するタイミングがくると、今までの頑張りがはっきりと合格・不合格という形で総決算される。試験の結果によっては「めっちゃ頑張ってたかもしれんけど、全然方向性違うから。」と言われるかもしれないと思うと、そりゃあ当然しんどい。年1回の試験なら尚更。私の場合は、試験3か月前にすごくしんどくなるんだな、ということが最近わかってきました。
昨年受けた、弁理士試験の短答式試験(一次試験)の3か月前(2月上旬)しんどすぎて、布団から出られなくなりました。結果と対峙しなければならない。これから答練や模試を受けていくにあたって、嫌でも今までの頑張りが正しかったのかそうでなかったのかについて、真正面から向き合わないといけなくなってしんどくなりました。丸三日ほど、ご飯もほとんど食べずに布団に入って、天井を丸一日眺めてました。
でも、ちゃんと対峙して下さい。自戒を込めて。予備校職員をしていた頃も、現実を直視するのを嫌がって模試受けなかった受験生たちは、ことごとく受かりませんでした(戦略的に受けないみたいな超一部の特殊なヤツは別でしたが。)
大体みんな「まだこの単元が終わってないので。」とか御託並べて逃げてた受験生はしょっぱかったです。当たり前ですが。
色んなものを犠牲にして努力してきた人に響く言葉はない
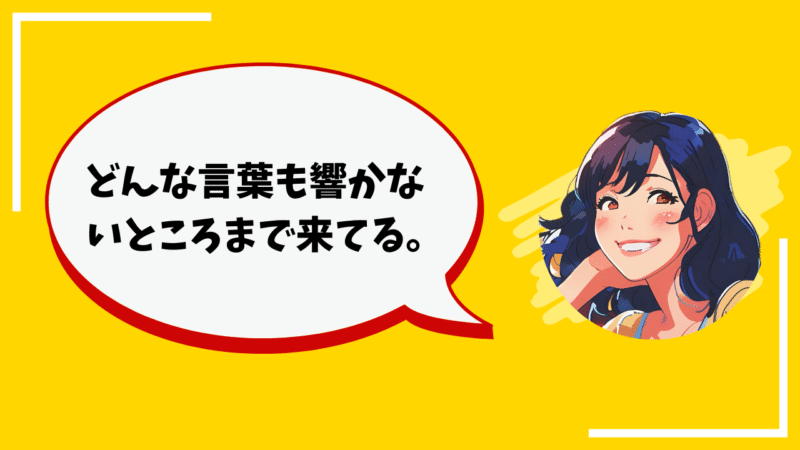
メンタルが壊れる生徒たち
前職は予備校で働いていました。国公立医学部受験生を担当していることが多く、たくさんの医学部受験生をみてきました。勉強に真剣に向かっている受験生は、全員が全員というわけではないのですが、秋ごろになると受験生のメンタルがおかしくなって、情緒不安定になる生徒が出てくるんですよね。
ボロボロ泣き出す子たちがいて、今、彼らの気持ちが非常によくわかります。今まで死ぬほど頑張ってきて、その結果と対峙するときがいよいよ迫ってきたのだから、そりゃあ追い詰められます。私が短答式試験前に動けなくなったのと同じだと思うし、短答式試験ほどじゃないけど、今年の選択科目、民法に関しても同じように追い詰められていて、「よくわかるよ。」って言いたくなります。
メンタルが不調な生徒が気持ちを吐露してきたときは、いつも数時間、黙って話を聴いてました。生徒たちは「もう受からないかもしれない。この生活からどう脱却すれば良いのかもわからない。」という趣旨の話をよくしていました。そのたび、私は「うまくいかなかったとしても死ぬわけじゃないから。」とか「医師以外にも仕事ってたくさんあって生きていけないわけじゃないから。」とか「不安になるのは受かる可能性がちゃんとあるからだ。」とかそういう類の言葉をかけていたけど、多分、彼らにはあんまり響かなかったと思います。それは、彼らがしている努力はたくさんの犠牲の下にあって、そんな言葉が響くくらいの生半可な努力じゃないからです。
彼らに響く言葉はない。
本気で受かりにきてる医学部受験生(弁理士試験受験生)って、本当に全部捨てている。そうせざるを得ないくらいの高い壁に向かって、立ち向かっていて、もはや受かるしかないという気持ちで挑んでいます。本当に全部捨てて闘っている以上、受からなかったとしたら撤退するという選択肢はあり得ないんです。受かるしか道はない。という感じです。
私が彼らに投げかけていたような外野の言葉は確かに正論だけど、本人からしてみれば狂気の世界で死ぬ気で闘っているわけで、常人がする当たり前の発言なんて、「そんなのあんたに言われる前に100万回考えてるわ!」って感じだと思います。「うまくいかなかったとしても死ぬわけじゃない」ことなんて知ってるし、「医師(弁理士)以外にも仕事がたくさんあること」だって知ってる。
その上で、尋常じゃない時間と労力をかけて挑んできた以上、合格するしか本気で道がないというのが正直なところなのです。私は彼らにかける適切な言葉を持ち合わせていなかったと思います。でも、外野側の言葉もよくわかります。どうにかして彼らの心を和らげてあげたいという気持ちから出る言葉なんですよね。
とはいえ、先人たちは全員乗り越えている
結局、自分で立ち直るしかない。
とはいえですが、先人(合格者)たちは全員それを乗り越えてきている、というのもこれまた事実でもあるんですよね。医学部に受かった人たちも弁理士試験に受かった人たちも平等に同じ苦しさを味わってるわけです。これは紛れもない事実です。
その上で改めて(自戒の意味も込めて)泣き言を言っている受験生のことを考えると、「私は先人ほど我慢できません。受かるかどうかの恐怖に打ち勝てないし、受かるほどの努力はできません。」って白旗を揚げて表明しているのと同じなんですよね。
泣き言を言いたいタイミングもあるし、言っても良いと思うけど、結局のところ、自分で立ち直るしかないと思うのです。はっきり言って、泣き言を言うスタンスは結構ずるいんですよ。「頑張れないけど合格はしたい」っていう虫の良い話をしているわけですから。それならちゃんと撤退していった人達の方が何百倍も潔いし、強いんです。中途半端なスタンスって一番ずるいことをしてるんですよ。
「先人ほど耐えられる心は持ち合わせてないけど、撤退はしたくなくて、合格はしたいです。」って言ってるのと同じですから。結局のところ、撤退の意思がないなら自分で立ち直るしかないし、立ち直って全力で走るしかないのです。走るのはあなたですから。
誰も「弁理士になりなさい。」なんて頼んでない。
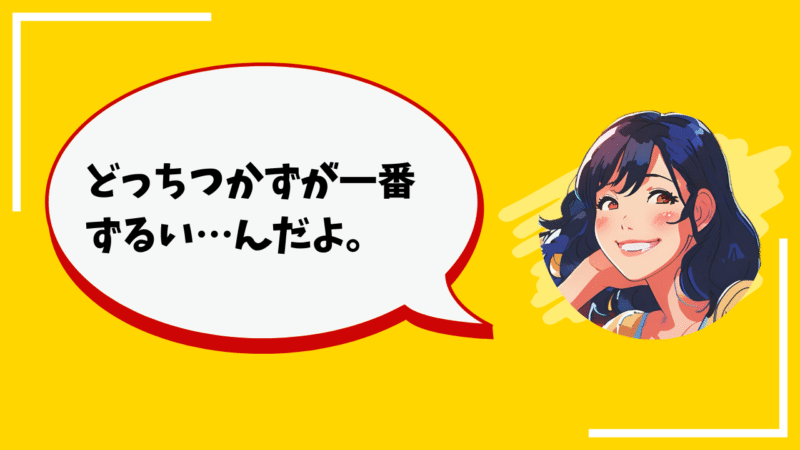
元を正すと、「医師(弁理士)になれ。」なんて誰も頼んでないし、手前が始めた話なんですよ。いつでも辞めて良いし、辞めても誰も困らないんです。
私が小学生の頃、ピアノが弾けなくて、練習するのが嫌すぎて練習をサボっていたときの話です。親に「誰も「やれ。」なんて頼んでない。やめたかったら、やめれば?」とよく言われてました。教則本「ブルグミュラー」をゴミ箱に捨てられることもしばしばありました。小学生の私はピアノを弾くのが嫌で嫌で仕方なくて、ピアノの響板に足を何度も何度も押し付けるから、実家のピアノの響板がやんわり曲がっています。
小学生相手になかなかシビアな親だったとは思いますが、反面、理には適ってるのも事実なんですよね。だって、「ピアノ弾いて下さい。」なんて頼んでるわけでもないし。
小学生の私からしたら、そんな言われ方したら弾くしかないやん!っていう、逃げ道が無さ過ぎてる感もまた否めませんが。反語です。反語。
でも、習わせてもらってる以上、私も練習する責務はあるわけですし、やめたければやめれば良いんですよ。どっちつかずでやってるのが一番ずるいし、自分自身の人生としても時間の無駄なんです。
これ以上どうしようもないところまで頑張ると不安はなくなる
昨年、短答式試験を受けに行ったときに「もう落ちても全然良い。仕方ない。」と本心で思ったんですよね。何でそんな風に思ったかというと、もうこれ以上どうしようもないくらい頑張ったし、テキストが真っ二つになるまでやり込んだ。問題だって50000枝解いたし、答練も自分の人生において、同じような経験はないくらいの成績を収めていた。だから、自分としては「これ以上もはやどうすることもできないところまでやった。」という感覚があったんですよね。
だから、心の底から人事を尽くしたつもりでした。人事を尽くしきったからどんな天命でも迎え入れるわ!というのを本心で思えた感じがしたんですよね。だって、もう本当にこれ以上どうしようもないですから。
だから、もし、医学部受験生や弁理士試験受験生に、表向きの言葉じゃなくて本心で声をかけるとするならば、「「もうこれ以上自分ではどうしようもないくらい頑張れた。」と思ったら、逆に結果はどうでも良くなる。」ということを伝えるかもしれません。まあただ、この理屈は厳しすぎるからやっぱり「うまくいかなかったとしても死ぬわけじゃないから。」とか「医師以外にも仕事ってたくさんあって生きていけないわけじゃないから。」とか「不安になるのは受かる可能性がちゃんとあるからだ。」とか言うんでしょうけど。
結局、何をやっても救われない。
決断とは「断つ」こと。
受験生って結局、受かるしか救われる方法がないんですよ。息抜きをしたって、どこまでも付き纏うのは「で、受かるん?」っていう気持ち。時間と労力をかければかけるほど、「ほんまに正しい道に進んでるんか?」「行き止まりなんじゃないか?」とうっすらとした疑念の気持ちがたまに湧いてきます。
それでもやる。遊びに出かけても、どこかで強迫観念みたいにサボってる罪悪感が付き纏い続ける。そんな生活を何年も続けて、全てを後回しにしてると、楽しく過ごしている周りの知り合い、友人に置いてけぼりにされているような感覚になって、段々すり減ってきておかしくなってきます。周りが日々を楽しんで、ライフステージを進めていく中で、自分だけ全く違う方向に全力で走り続けるというのは外野から見てキツそうだなと思う以上に何倍もキツくて、孤独で、精神力が要る。自分で自分の生き方を信じる心、他を切り捨てる覚悟みたいなのが要る。決断というのは何かをするって決めることではなく、他の全てを断つことなのです。
合格するために求められている素養
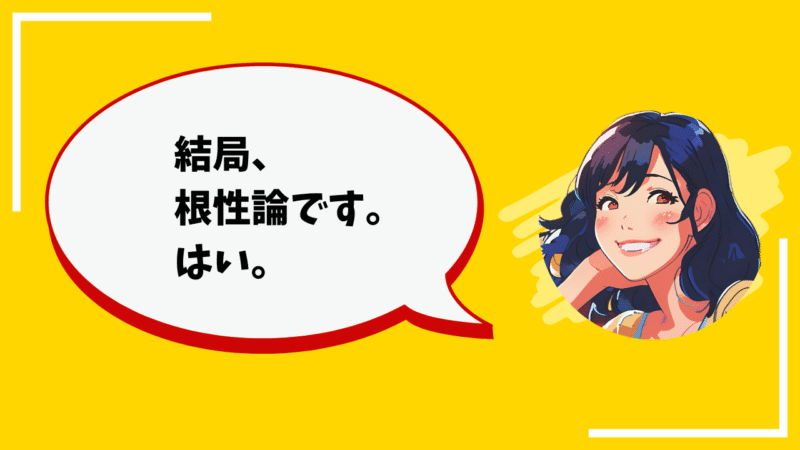
仕事から帰ってきて、何も考えずにお酒を飲んで、映画を観てたい。休日も、図書館かガストしか行かない生活はもう止めて、普通に過ごしたい。勉強ばかりしてると、「勉強好きなんですね。」って言われるけど、そんな訳あるかよ笑 と言いたくなります。跳ね返ってくるリターンが大きいことを知ってるから、我慢して全力で勉強を楽しもうと努力してるんです。誰が仕事から帰ってきて、難解な文章と法文集照らし合わせて何度も何度も読みたいです?
毎日、毎日、机に向かい続けて、何時間も論文を書き続けるガチガチの食傷さ加減。難解な文章を読み続けるのが嫌っていうより、「それで報われるなら頑張るけど、全部徒労に終わったら…。これで生き方あってる?」って感じになるんです。
毎月実施される試験だったり、落ちても次があるからっていう試験ではないというのもかなり厄介な要素であったりもします。ミスったらもう一年この生活(生活全捨て)をすることになるというキツさが医学部受験や弁理士試験にはあります。やれば全員報われるんだったらどんなに気楽なものかと思いますが、現実はそんなに甘くありません。試験合格のために求められている素養というのは、やっても報われるかどうか不明瞭なものに対して全力で挑める強さ、即ち、忍耐力だと思います。つまり、報われない可能性に心を折られてしまう柔な人間は合格する資格がないということです。
裏を返せば、だからこそ弁理士試験は価値のある資格だとも思います。弁理士に限らずですが、もし周りに「羨ましいな。」と思う人がいたら、その「羨ましいな。」と思ったのと同じ分だけ泥を啜っていたということなのです。でも、やめたかったらやめても良いと思います。中途半端にやってる人生が一番無駄です。人生は有限です。そして、人生は割と等価交換です。
だいぶしょっぱい記事でした。私も気持ち的にも超しんどいし、潜水します。では。

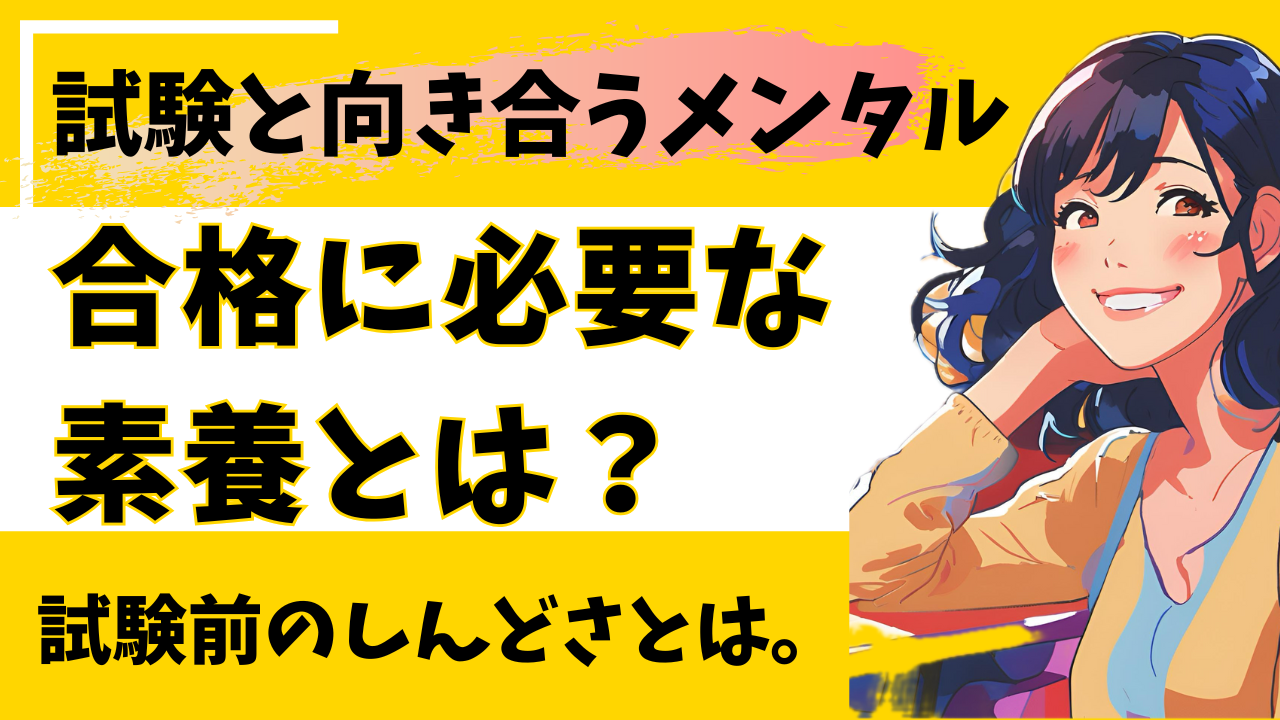
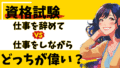
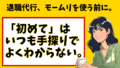
コメント
私はいま公認会計士試験の論文式試験が3か月後に控えており、メンタルやられてるのでとっても共感しました。。!!!
これからもブログの更新楽しみにしています
まいさん、こんばんは!コメントありがとうございます。公認会計士試験ですか。めちゃくちゃ大変だとお聞きします。自分のことを信じて、やってきたボロボロのテキストを持ち込んで殴り込みかけましょう。結局、受験生って受かるしか報われる方法がないので、やるしかないですよね。コメントいただき、ブログ更新の励みになります。ぜひ合格したら教えて下さいね(>_<)