青い蛍光ペンと彼女
青い蛍光ペンとカフェラテと彼女

31歳、独身。特許事務所勤務。
彼は仕事を終えると、いつものように法文集と論文過去問集を詰めた重たいバッグを持って、近所のカフェに向かう。店員はもう顔なじみだ。
「いつものカフェラテですね」
「うん、お願いします」
窓際の隅、コンセントのある席。青い蛍光ペンで過去問に印をつけながら、ふと視界の端に揺れる髪が見えた。
そこには、何度か見かけた女性がいた。小柄で、髪をひとつにまとめている。いつもパソコンを開いて何かを書いている。多分、物書きか何かだろう。
その日はたまたま隣の席が空いていた。彼女は軽く会釈して座り、パソコンを開いた。
「…弁理士試験、ですか?」
「え? あ、はい。なんで分かるんですか?」
「前に私も特許事務所でバイトしてたんです。論文、ものすごく大変ですよね」
話してみると、同い年だった。今はフリーで、技術系の書籍や記事を編集しているという。
彼女が帰る時、「頑張ってくださいね」と微笑んで言った。声も表情も、妙に胸に残った。
それから数日、また彼女を見かけた。言葉は交わさなくても、会釈だけでなんだか気持ちがほどける。
ある夜、いつもよりも少し遅れてカフェに入ると、彼女が先にいた。空いているのは、彼女の隣の席だけだった。
席に着くと、彼女がそっと紙ナプキンを滑らせてきた。そこには、こう書かれていた。
「今度、勉強終わったあとで少しだけ話しませんか?カフェラテ、奢ります。」
蛍光ペンを持つ手が止まった。
なぜだか、胸が熱くなった。
過去問集のページの端が、少し震えた。
紙ナプキンに書かれた彼女の文字は、やわらかくてまっすぐだった。そして、ほんの少しだけ照れくさそうな感じがした。そっと裏返すと、裏はまだ白い。
しばらくそのナプキンを見つめていたが、ふっと笑って、青い蛍光ペンのキャップを閉めた。
彼女はまっすぐパソコンを見つめていた。彼はそっと彼女に声をかけた。
「あの…もしよかったら…今、少しだけお話しできたりとかしますか?」
彼女はほんの少しだけ驚いた顔で彼を見た。そして、すぐに笑って、そっとパソコンを閉じた。
「紙ナプキンはちょっと古風すぎました?それじゃあ、約束どおり、カフェラテ、奢らせてください」
「ありがとうございます。遠慮なく、ホットでお願いします」
カフェラテの湯気の向こうにある彼女の横顔を見ながら、「試験勉強も悪くないな」と、ぼんやり思った。
「試験、もうすぐなんです」
「うん、顔に書いてある」
初めてカフェラテを奢ってもらったあの日から、二人は色々と話すようになった。
お互いの仕事のこと、学生時代のこと、最近聴いている音楽や、子どものころの習い事まで。
話題はごく普通。でも、そんな“普通”が彼には沁みるほど心地よかった。
彼女はよく笑う人だった。そして、「頑張ってる人を、ちゃんと応援したい」と自然に言える人だった。
そんな言葉に背中を押されるように、勉強の手も止まらなくなった。
いつしか、青い蛍光ペンのインクはほとんどなくなっていた。
試験が終わった日、彼はまたあのカフェに行った。
椅子に座ると、彼女が気づいて、嬉しそうに小さく手を振った。
「お疲れさま。どうだった?」
「手応え……あります。でも結果はまだ。とりあえず、生きて帰ってきました」
「じゃあ、今日は私がまたカフェラテを」
「いや、今日は……僕が奢らせてください」
二人は並んでカップを持ちながら、窓の外の夕焼けをぼんやり眺めた。
沈黙すら心地よくなってきたころ、彼は少しだけ躊躇ってから、言った。
「この数ヶ月、実はすごく救われてました。……だから、試験が終わっても、また会えたら嬉しいです」
彼女はカップを持ち直して、軽く頷いた。
「……私も、そう思ってた。じゃあ、今度は勉強抜きで、どこか行こうか」
カップの縁から、湯気がひとすじ昇った。
その中で、彼女の横顔が、少しだけ照れて見えた。
なんてことはまるでない。
彼は独り、カフェでモーニングを食べながら、論文を書き続ける。
青い蛍光ペンのインクは今日もまだまだ減らない。
青い蛍光ペンと白い封筒と彼女

嵐のような弁理士試験に向けた勉強の日々が過ぎ去って、早一ヶ月が経とうとしていた。日常の静けさを取り戻したはずの彼はまだあのカフェに通っている。
「いつものカフェラテですね」
「……はい、お願いします」
彼女は、やっぱりいなかった。
最初から、いなかったのだ。
気づいていた。あの日、カフェラテを奢ってもらった。肩を並べて色んな話をした。パスタの中だと、トマトパスタが好きだけど、トマトパスタに入ってる茄子が嫌いだということ。映画はどんなストーリーでも良いけど、最後はハッピーエンドじゃないと観たくないということ。全部、自分が作り上げた妄想だった。
それでも、彼は来てしまう。
彼女と過ごした“気がしていた”時間を、確かめるように。
ポケットに忍ばせたままの、使い切った青い蛍光ペン。インクのないそれを握りしめると、あの日の感触がちゃんと蘇ってくるような気がして少しだけ心が落ち着いた。
妄想だったくせに、カフェラテの湯気の向こうにある彼女の横顔も、彼女の声も、紙ナプキンの触り心地までやけに鮮明に思い出せてしまう。記憶の中の彼女は、いつも見守るように微笑んできて、彼の心の柔らかいところをきゅっと掴んだ。
自分が勝手に作ったはずの存在なのに、彼は、あの横顔に何度も救われていた。
「……やっぱ俺、ちょっとやばいな」思わず自嘲気味に笑った。
席を立ち、レジへ向かう。すると、店員が小走りに追いかけてきた。
「お客様、これ……テーブルに置き忘れられてました」
差し出されたのは、白い封筒。封もされておらず、宛名もない。かすかな期待にも似た予感が、妄想と現実の狭間を行き来する彼の手のひらに汗をにじませる。
中には、一枚の便箋。見覚えのある、柔らかくてまっすぐな字。
「お疲れさまでした。あなたの記憶の中だったけど、すごく楽しかったよ。合格してるといいね。」
便箋を持つ手は震えていた。頭を殴られたかのような感覚に襲われてしばらく動けなかった。気づけばバッグも持たずにカフェを飛び出していた。周囲を見渡した。
──が、それらしい姿はどこにも見当たらない。
財布を開いて、指先でそっと慎重に取り出す。あの日くれた紙ナプキン。
あの日の記憶が刻まれているはずの──
ただの真っ白な紙切れだった。
何も書かれていない。
何も、残っていない。
彼は、その紙を見つめながら、宙に向かってぽつりと呟いた。
「……あれは最初で最後の、応援だったのか……」
ポケットに入れたままの書けなくなった青い蛍光ペン。でも、手放すにはまだ早い気がした。
何も書かれていない紙ナプキンをしまい、カフェを後にした。
まだ十月だというのに、夜になるとどこか冬の空気を感じさせるくらい風がやんわり冷たい。きゅっと身体を縮こませてぽっかりと空いた何かを埋めようとする。このまま家に帰ってしまうと、上手く息ができなくなりそうな気がして、公園のベンチに腰を下ろした。
封筒をもう一度取り出し、便箋を取り出す。彼女が残した言葉を見ていると、便箋の下の方に、何かインクの跡が残っていることに気づいた。指で軽く擦ると、かすかに文字が浮かび上がってくる。
「追伸:あの日、私は本当にあなたの隣に座っていたよ。私こそあなたに救われていました。」
一瞬、鼓動が跳ねる。けれど、すぐさま思い返す。誰かのいたずら?それとももしかして…
ポケットの中で、使い切った青い蛍光ペンが転がった。
ポタッと大粒の雫が空から落ちてきて、便箋に乗ったインクが滲んだ。彼はベンチから立ち上がった。そろそろ帰ろう。
足早に駅までの道を歩いていると、前から来た女性とすれ違った。その拍子に、女性のショルダーバッグに目がとまる。あのショルダーバッグだ。
──青い蛍光ペンが、ポケットに差されている。
思わず振り返る。
が、彼女はすでに都会の夜に溶けてしまって、その姿は見えなかった。
ポケットの中で、彼の青い蛍光ペンが、カチッと音を立てた。
白い封筒と青い蛍光ペンと彼

いつもの席に、彼は今日も座っていた。
法文集を開いて、黙々と文字を追い、青い蛍光ペンでゆっくりと丁寧に線を引く。その眼差しを私は何度も見てきた。
彼の記憶の中で、彼の傍らで。
⸻私は、彼の記憶の中にいる存在だった。
最初に私が”私”の存在に気づいたのは、彼が初めてこのカフェに来た日。窓際のコンセントのある席に座り、重たそうな法文集を開いたその瞬間。彼の目がふと宙を見て、何かを探すように揺れたとき、私はその空白に入り込んだ。
声をかけたこともある。「……弁理士試験、ですか?」彼は驚いて、でも嬉しそうに笑った。嬉しそうに笑ったときの顔は写真にできるくらいはっきりと覚えてる。だけど、これは私の記憶じゃない。彼の記憶が作った私。
ほんの少しだけ寂しかったけど、その代わり、私は何度も、彼の横に座ることができた。
⸻彼が望むときだけ。
彼の脳裏が静かに、誰かを必要としたときだけ。
だけど、私はだんだん、彼の記憶の世界じゃなくて、“彼自身”に会いたくなってしまった。どうしようもなくじれったくなって、心が疼いた。触れたいと思った。
ちゃんと本当に、彼の目を見て、彼の隣で言葉を交わしたいと思った。
だから、私は、あの日一度だけ、記憶の中じゃなくて、現実に会いに行ったんだ。
彼は最初、私を見て目を丸くして驚いた。だけど、何も言わずに記憶の中と同じように、自然に、何の違和感もなく会話をしてくれた。
初めて会ったのに、「普段妄想してた人とそっくりです」なんて言えないか。
私はそっと、紙ナプキンにメッセージを書いた。彼は何にも気づいてなかったけど、本当は手が震えて何度も何度も書き直したんだ。滑らせるようにしてそれを渡したとき、彼がメッセージを読んでニコッと笑ったのを見て、「本当に来てよかった」と思った。それが、最初で最後の“現実の彼”との時間。
それ以降は、もう戻れなかった。きっと彼の中で、私の存在が少しずつ小さくなっていったのだと思う。でもそれでいい。それでも、彼の中に何かを残せたことが嬉しかったから。
冬の足音が聞こえてきそうな十月の夜、私はもう一度だけ、カフェに行った。だけどもう姿を見せることはできなかった。だから、白い封筒を、彼のテーブルにそっと置いた。
名前も、差出人もない、白い便箋。
そこには、こう書いた。
⸻
「お疲れさまでした。あなたの記憶の中だったけど、すごく楽しかったよ。合格してるといいね。」
⸻
伝えたかった。私の気持ち。
もう一言だけ、わがままな私はどうしても伝えたくて追伸を添えた。
「追伸:あの日、私は本当にあなたの隣に座っていたよ。私こそ、あなたに救われていました。」
封筒を置いて、カフェを出る。彼が店員さんから封筒を受け取る様子が窓越しに見える。だけど、背中を向けていて表情が見えない。
封筒を受け取った彼はしばらく立ったまま動かなかった。
「どんな顔をしてるんだろう」と思って、後ろ姿を見ていると、彼が急に振り返った。ほんの一瞬目があった⸻気がした。
バッグも持たずにカフェの外に出て、すぐ横にいる私を必死に探している。ここにいることをどうしても伝えられなくて、悔しくてたまらなくなる。
ハッと何かに気づいた彼がゆっくりと財布から丁寧に折り畳まれた紙を取り出す。
まるで、それが宝物であると信じて疑わないように。
⸻あの日渡した紙ナプキン
彼の隣で、まるで小さな子どもみたいに大声で泣きじゃくった。
彼の中にちゃんと私が残ってることがたまらなく嬉しかった。
嬉しくて、悔しくて、悲しくて涙が止まらなかった。
青い蛍光ペンのインクが切れて、彼が試験に合格したら、私はきっと消える。それでいい。
彼の人生が、この先ほんの少しでも軽くなったのなら、私はそれだけで、ここにいた意味がある。
⸻ありがとう。
思い出してくれて。
あとがき
あとがきは別記事で書きました。読んでいただけると嬉しいです。


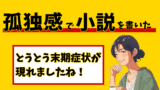
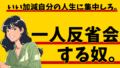

コメント