いける!と思うことと、ナメてかかることは表裏一体
自分ならいけると思うことは大事だが…
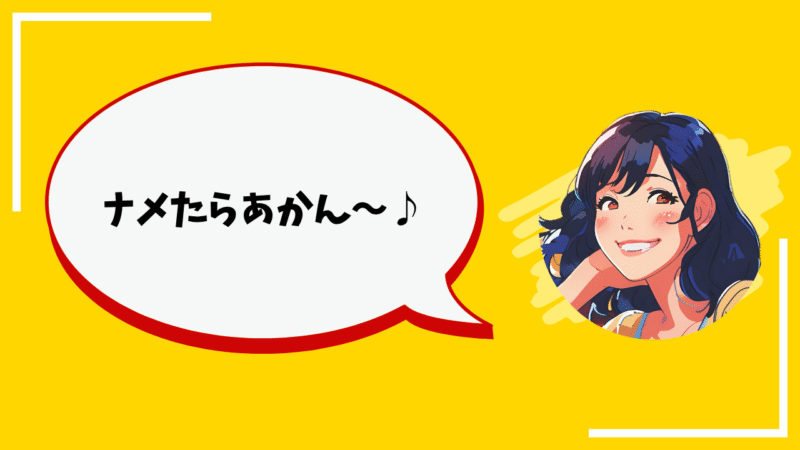
どうも、ニシジマです。今日は、合格しそうなときの試験に対する正しい向き合い方についてお話をしようと思う。結論から言うと、
「いける!と思うのは大事だが、ナメ始めた瞬間に落とされる」ということだ。大学受験でも、資格試験でも一番良いメンタルというのは、順調にやって本番ちゃんと力発揮できたら確実に受かると思うけど、それでもまだ少し不安だという気持ちを抱えているくらいがちょうどよい。
模試でA判定を出しまくったり、もうどんな問題が来ても横綱相撲を取れるような状況に差し掛かったときに、人間は試験をナメ始める。なぜナメ始めるかというと、緊張状態を持続するのがしんどいし、やってきた自負があるからだ。でも、言っておく。お前はまだ何も成し遂げていない。合格を掴んで初めて「成し遂げた」になるのである。
A判定を取りまくっていようが、どんな問題が来ても戦える力をつけていようが、本番で落ちたらそれまでだ。誰も認めてはくれないし、今までの積み重ねてきた努力やA判定は水の泡になる。ゴールテープが見えると人間は気が緩むことを肝に銘じよう。
達成して初めて成し遂げたことになる

よく大学受験で「〇〇落ち」みたいな表現を聞くが、「〇〇落ち」なんて何の意味もなさない。そんな称号は何の努力を重ねなくても取れる。誰でも受ければ「〇〇落ち」だ。受かって初めて価値が生まれる。当落がはっきりしていてすごくシビアな世界だと思う。
そこまで努力を積み重ねてきたことも重々わかる。その上で改めて考えてみよう。目の前にゴールテープがやっと見えたとき、君はきっと思う。「おぉ…やっとゴールが見えた…。今までの努力が報われる瞬間だ…」疲労困憊でパンパンに腫れた脚がもう動かなくなりそうになる。ここでちゃんと脚力をもって走り切れるか、ゴールテープを前に脚力を落としてしまうかは、まさしく人間力だと思う。最後の脚力に人間の分厚さの違いが如実に表れていると思う。
そして、ゴールテープを見ても、なおも走り続けた人間だけが本当にゴールテープを切れる。ゴールテープを目の前に気を抜いた人間は、字のごとく、格が合わなかったのだ。格に満たない人間だったから落ちるのである。何回でも言ったるわ。だから落ちんねん。
実力が発揮できなかった?実力をどうすれば最大限発揮できるか想定しなかったからじゃないか。「ゴールテープの微笑み」を無視して走り続けるのだ。
ちなみに、北島康介もこの「ゴールテープの微笑み」に弱かったらしくて、ゴールを、壁を振り返って電光掲示板を見ることにしたらめちゃくちゃ伸びたらしい。
「憧れ」は良くない。ナメてかかることで行動力が生まれる
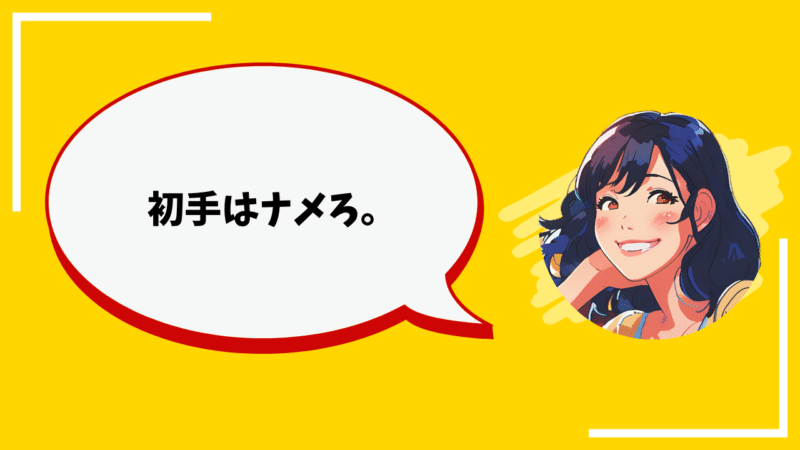
世間では「憧れ」という言葉をプラスの意味で使っているような気がする。だが、「憧れ」というのは結構微妙だ。私はむしろ憧れないくらいの方が物事は達成できると思っている。
憧れているということは、自分よりも上だと認めていることになるからだ。自分より上だと認めた途端に、憧れの対象がすごく遠く感じるようになる。さっきはナメてかかるなと言ったが、初手はむしろナメてかかる方が良いと思っている。つまり、初手はナメろ。本格的にやり始めたらナメるな。これが私が思う、物事の成功法だと思う。
そう、初手はナメるのである。私も弁理士試験を完全にナメていた。
「暗記するだけやろwこんなん1年あったら受かるわ!」
豪語していた。いや、誰かに言ってたわけじゃないけど、難関過ぎるとかマジで大袈裟よなーと思っていた。実際取り組み始めて、法律を理解していく難しさや複雑さ、理解するためにはとんでもない根気が必要であること、色々なことを学んだ。でも、初手で「いけるやろ!」とナメずに憧れで終わっていたら、憧れたままずっと一生線引きしていたと思う。
線引きするのは楽だ。頑張らない理由ができるから。でも、それで良いのか?もう今まで何百回、何千回と線引きしてきただろう。その線引きする姿勢をこれからも続けて死んでいくのか?もう一回自分に問いかけてみよう。

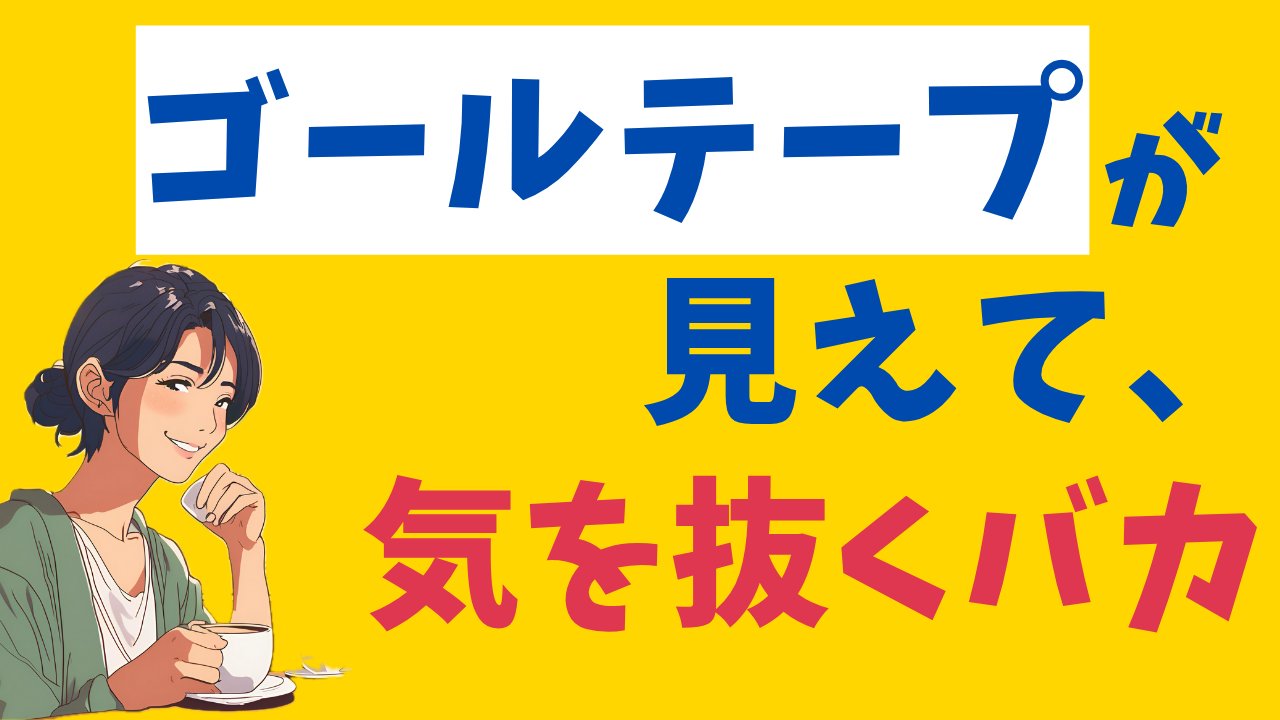
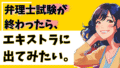

コメント